BOOK 2
【101-130】
岡本浩一/PHP/219ページ/1997/97.5.9
「自己実現イコール仕事の成功」ではないと社会心理学者の著者.岡本氏は断言する。日常生活に於ける物足りなさを仕事や会社だけで穴埋めすることは出来ないのである。この穴埋めを行うのが氏が提案している「複線型人生」つまり、仕事とは全く独立して複線型アイデンティティを推進し、深い趣味「キャリア型趣味」を持つことによって会社とは別の自己アイデンティティを確立しようとするものである。無趣味で仕事に対して有能な人ほど「仕事ナルシシスト」に陥りやすく、その事が自分の人生のみならずに家族や他人をも不幸に巻き込んでしまうことさえある。それを避けるためにも「キャリア型趣味」の必要性を訴えている。氏はこの中に通常、趣味と考えられている読書、英会話、旅行、パソコン、インターネット、仕事や金儲けなどを入れていない。基本的には短時間でも道具なしで休憩出来ることを「キャリア型趣味」の条件に挙げている。これには若干の異論はあるがその後に書いてある茶道や将棋、囲碁などのページを読むとそれらに造詣が深い氏が言うことも宜成るかなと思う。岡本氏は経歴を見ると日本の高校とアメリカの高校の両方を卒業している。コミュニケーションの手段としての英会話が趣味にならないことと氏のキャリア型趣味に日本文化に関わるものが多いことはもしかするとこの辺から起因しているのではないか。これは私自身の経験なのだが自国の文化を一番痛感させられるのは実は外国人と接している時なのだ。そして同時に如何に自国の文化を自分が知らないかも思い知らされる。氏はアメリカにいた時にこの事を身に沁みて感じ、帰国しただろうことは想像に難くない。アメリカ人は良い意味でも悪い意味でも自己アイデンティティーを確立している。そして、両国の文化に触れた氏の述べる「複線型人生」は「キャリア型趣味」の構築を中心に書いていながら実際は仕事と趣味をバランスよく楽しむことが自己実現に繋がるというが結論になるのだと思う。これまで無趣味で走り続けてきて現在、仕事に息詰まっている方は是非一読下さい。
宮本政於/講談社/325ページ/1997/97.5.17
実は私も読む直前に本書の冒頭にある宮本氏と同じ事を考えていた。それは日本には「思考する人間」がいないのではないかという疑問である。「労働する人間」は大多数の国民でそれを支配しているのが「何もしない人間」の官僚達という図式で日本社会は成り立っている。小さい頃から去勢を施すような教育をし、仕事の中に国民を埋没させ、「滅私」という鞭で国民を打ち続けるのが官僚である。彼らにとっては「自分の生活」を主張し、日本のみ成らず、特に外国で自分達を陥れる存在だった宮本氏は絶対的に洗脳するか排除せざろう得なかった人間の一人だったのだろう。そして遂に陰険な笑みと共に「懲戒免職」という形で彼らの目的は達成された。そして、解雇させられた宮本氏を支えたのは「組織」の論理に染まった民主主義とは形だけの日本人ではなくて、大半が「個人」先ずありきの本当の民主主義が生きづいている外国人達であった。日本ではマスコミも含めて、社会の大部分の組織に属する人々が拒否反応を示した。日本は本当の意味での「自由」を獲得していないという事実がここに如実に現れている。氏は現代の「ドンキホーテ」として果敢に官僚組織に挑んだ。だが、それをサポートするのがほんの一部の日本人と多くの外国人では余りにも哀しい。こんなところにも知識人などと大上段に構え、実のところ何にもやっていない人々がマスコミで大きい顔をしていることが「思考する人間」のいない日本の現状を示している。これ以上、官僚に支配されることを我々国民は望んでいるのか。官僚の奴隷になるように洗脳され続けることを潔しとするのか。我々国民の多くが怒りを持ってこの人間らしい生活を渇望しなければ、日本国の変化は未来永劫に期待出来ない。これは私自身のエピソードで恐縮だがそれは官僚のプライドに関わるもので前仕事に於いて東京都の交通局にある資料を要求したところ、都の人間でないと要求には応えられないと言う返事だったので「日本国民である以上、資料を要求する権利はあるのではないか」と少し憤慨して聞いたところ、どうしてもそれは出来ないという如何にも事務的な対応の後で怒りに震えながらも受話器を置いた。だが、話はそれだけでは終わらずに後日、私が以前から進めていた札幌市交通局での仕事がどういう訳か中止されてしまった。何故かと担当者に尋ねると突然に東京都交通局から電話が入り、あの業者とは取引しないよう言われたとの事であった。都の職員は自分の面子を守るために地方交通局に圧力をかけたのだった。「汚い」と思いながら感情的な対応しか当時の私には思い浮かばなかった。到底納得出来なかったがこれが官僚を含めた公務員の姿なのだと仕事(会社)を考えると現実を直視するしかなかった。その溜飲が下がったのが宮本氏の著書「お役所の掟」を読んだ時であった。それ以来、氏の著書は欠かさず読んでいる。是非、組織に埋没することを良しとしない日本国民には一読願いたい。(宮本氏の他の著書としては「在日日本人」(ジャパンタイムス)、「お役所の御法度」(講談社)などがある。)
田原総一朗/文藝春秋/253ページ/1997/97.6.2
岩波映画から東京12チャンネル(現テレビ東京)を経て、テレビメディアの発達と共に歩んできたというよりその発達に常に手を貸して続けてきた田原氏。本書の中で一番興味深い部分だったのは「東欧を変えたのはノイズだった」という177ページから述べられている所である。氏はクロード.E.シャノンの言葉を取り上げて「コミュニケーションの記号は物事の本質から見て不要なノイズと必要で有用なものシグナルに分けられる。そして、このシグナルがインフォメーションである」これまで一般的にはこれが通用していたがテレビの台頭によりこれまでノイズとされてきたものがシグナルとされ、あるいはシグナルとされていたものがノイズとされていると語る。また、ノイズとシグナルの区別がなくなり渾然一体となっているのが現在の情況だと言う。そしてまさに西ドイツのノイズだと思われていた車のCMが東ドイツにベルリンの壁を崩壊させた原因だと田原氏は述べている。確かに新聞を中心とする活字社会に於けるノイズとテレビを中心とした映像社会のノイズは異なっている。その反対に現代人にとってのシグナルとテレビメディアが発達する前の人々のシグナルも違っていることだろう。それは物事に対する価値観かもしれない。それから田原氏は偏向報道による椿氏の事件を取り上げ、言論機関としての自制と責任は必要だが同時に報道機関としての「放送による表現の自由」を守ることも大切だと力説する。私も1950年に作られたGHQによる法律に因らずともこの表現の自由は守られるべきだし、最大に尊重すべき事項だと考える。その後には氏が創ったと言っても過言ではない「朝まで生テレビ」の誕生秘話や苦労話が書かれている。あの文化的には不毛であった深夜番組枠に討論番組を堂々とそれも4時間も持って来たのは氏とスタッフの大英断であったと思う。本書を読み、これからも政治や経済に限らずにテレビ業界全体のあり方に拘り続ける田原氏の姿勢を応援して行きたい。これからもし、テレビ業界に入りたいと思っている若者には是非、本書を手に取り、そして腰を落ちつけて読み、氏を超えるような拘り続ける番組作りをする事に期待したい。
斉藤学/講談社/252ページ/1995/97.6.5
この本を自分の事として真剣に読んだ人は帯にある新聞社の書評が実に上辺だけの陳腐なものだということが分かるだろう。何故かというとおそらく、その人自身が本書に度々登場する「仕事依存症」の男達だからだと思う。これを書いている私自身にも何々依存症というのはあるかもしれないが間違えても仕事依存症にはなっていない自信がある。さて、本書には様々な問題が挙げられているが根本的には男と女の問題、つまり男が女の世話焼きを必要とし、女が男に必要とされる世話焼きをする必要があるという事である。それを具体的に説明するため斉藤氏は「家族」を取り巻くアルコール依存症、登校拒否、共依存症やアダルトチルドレンなど現代に進行する精神異常を取り上げているのだと思う。この中で結婚する男と女の間に常に横たわる問題としては「育児」が最大のものであろう。これまで日本では女の母性に押し付ける形で子供の育児を殆ど彼女らに任せていた。男は仕事を楯に取り、育児を蔑ろにし、育てられた子供の責任を全て女に擦り付けてきた。この父親不在の状態が今まで日本では経済的な事にかまけて、この状態が良いのだと世間でも認めている部分があった。だが、現在の子供達を見てみるとそれは間違えであったと考えさせられる。それは決して子供だけではなく、大人と呼ばれている人達にも波及している。つまり、父親、母親、子供それぞれの心の中はとても空虚で斉藤氏も述べているように形骸的に家族を形成しているに過ぎない。もしかすると母親は父親を通じて世の中という大きな男に必要とされていると感じ、その期待に応えるために子供を育て、父親の世話を焼き、家族を作っているのではないのだろうか。父親は「家族のために」と口では言いながら家族に対する責任を放棄し、「仕事」という女に自己の世話焼きを頼んでいるのである。しかし、その仕事という女は最近、自分のことをリストラや会社ぐるみの悪事などにより葬り去ろうとしている。確かに自分の人生を対象(物や人)に委ねてきた人々にはどん底の苦境かもしれないが「男とは」「女とは」「子供とは」「家族とは」などという本来の人生の命題をじっくり考えるには最適の時期だと思う。人間は理想だけで生きてはいけないがさりとて金だけでは心の充実を得られない。本書は問題を曖昧にせず、自己と本当に向き合うことに対しては一助となり得るだろう。
松木麗/講談社/230ページ/1997/97.6.8
松木嬢もあとがきで書いているが警察と裁判所は一般によく知られているのにその橋渡しをする検察庁は意外と知られていない。著者は「司法解剖」と「精神鑑定」という検事がこんな事もするのかという2つの題材から自身の経験を基に説き明かしている。私は常々弁護士や検事になる人達は学校を優秀な成績で卒業し、何の苦労も知らず、社会経験もしないままで人を裁くということに大いに疑問を抱いていた。それが彼女の上司だった「オネスト.ジュン」という真っ正直なN検事正の存在によって少し氷解した。こういう人々が上司にいることにより経験の少ない検事見習いともいうべき人が人間的にも成長していくのだと納得した。又、彼女の人間性を示すエピソードとして精神科医を目指していた高校時代のことを挙げている。そして、ある生物フィルムを見たことにより方向転換し、検事の道を歩くことになる。なんと気絶してしまったのだ。だが皮肉なことに検事になって「司法解剖」という場面に立ち会い、生物フィルムよりもっと恐ろしい凶悪事件に於ける死体と対面することになる。気絶を乗り越えた彼女だったが人間の根元としてそこでは死体にも魂があり、その魂に手を合わせることを学ぶ。それともう一つの題材「精神鑑定」で男女様々な被疑者に出会い、それぞれ一筋縄ではいかない鑑定の困難さを痛感している。特に有罪と無罪を分ける最大の要因これは宮崎事件でも問題になったが犯行当時の「心神喪失」と「心神耗弱」すなわち責任能力があるかないかという事である。犯行当時に「心神喪失」と鑑定されれば「無罪」で精神病院送り、「心神耗弱」と鑑定されれば情状酌量の余地があるとはいえ「有罪」。この間にある大きな溝に人間としての彼女の苦悩がある。松木嬢を通して裁く側の人間も裁かれる人間にもそれぞれドラマがあり、それを簡単に事務的には処理出来ない仕事であると再認識させられた。本書には松本嬢の検事としてと言うよりは人間としてのドラマが強く感じられた。
五島勉/青春出版社/226ページ/1990/97.6.14
現代の予言者エドガー.ケイシーはつい最近、ノストラダムスと共に日本テレビ系「知ってるつもり」の特別番組で取り上げられたのでご存じの方も多いだろう。そして、この分野の先駆者である五島氏は今から7年前にこの人物の恐るべき予言を既に解読していた。その予言とは「日本が1998年に沈む」という我々日本人にとっては驚天動地の言葉であった。氏はこの予言がアメリカに行っていたある広告代理店の愛読者により欧米で噂程度であるが一部の人々の間で囁かれているとの事実を聞いた。この事実によって五島氏はエドガー.ケイシーという人物を掘り下げなければならなくなった。旧約聖書、新約聖書、ノストラダムスと丹念に対比させながら氏はこの予言の本質に迫ろうとしていた。ある程度の結論を導き出しながらも一方で五島氏はニューヨークに住むジャーナリストに頼み、ケイシー予言の正確な原文の入手を計る。その原文は次のようなものであった。「the
greater portion of Japan must go into the sea」(日本のより大きな部分は沈まなければいけない)-これは予言というよりは誰かの願望であると氏は推測し、それは白人である一個人のケイシーというよりはもっと多くの人々-欧米の白人、特にWASP(White
Anglo-Saxon Protestant)達の集合無意識と深層心理によるものであると一様結論づけた。しかし、氏がこれを解決するために本当に心の底から望んでいた事は新しい日本人の強い深層の意思により彼らの思惑を打破することであった。1998年に後1年と迫った現在本書を読むことは当時以上に恐怖感が煽られるし、状況がその当時と比較してももっと堕落してしまった日本人を見るにつけ、欧米=白人の術中にはまることは時間の問題であると絶望感すら覚える。本書を興味本位ではなく、洞察力の鋭い読者に一人でも多く読んでもらい、私も含めて五島氏の切望する強い深層の意思を発揮出来る日本人に生まれ変わろうではないか。
小此木啓吾/大和書房/254ページ/1995/97.6.15
小此木氏が最初に書いてある通り、マクロにパーソナリティが狂っていることは他の人の目にも一目瞭然だがミクロに狂っている一見正常人の様な人が周りの人々を困らせることになるのである。氏はこれらの人々を具体的な例を挙げて、詳細に説明している。気の弱い人、心細い人、激情の人、いつもいい子の人、自我の強い人、自分だけの人、いつもパフォーマンスの人、悲劇のヒロイン、身体で演じる人、疑い深い人、思い込みの人、人見知りする人、几帳面すぎる人、潔癖症の人、縁起をかつぐ人、さぼる人、いじめる人、いびる人、尽くす人、不幸な人、破滅型の人。それぞれのパーソナリティは単独というよりは相互が複雑に絡み合っていることが多い。そのミクロな心の悪魔が他人を不幸に導くと共に自分をもその世界に引きずり込もうとする。これらの項目が自分に当てはまると感じたら(殆どの人はなんらかの項目に当てはまると思う)本書を熟読し、自分自身で再認識し、それから解決方法を探って欲しい。それにしても最近は困った人のオンパレードという感のする日本列島である。
江夏豊/小学館/222ページ/1997/97.6.19
江夏氏の著書はこれまでに数冊読んだがいつも氏に感じることは野球に対する飽くなき情熱である。江夏氏はある事件を起こし、刑務所生活を余儀なくさせられた。それは自業自得というものであったと思う。しかし、この様な世間に顔向けが出来ない生活を通しても氏の野球に対する愛着心は変わることがなかった。2年前に江夏氏が出所して、一番最初に心に飛び込んできたのが野茂が大リーガーになった事であった。それは自分自身が36歳で挑戦し、果たせなかった夢でもある。氏は微妙な感覚の違いがあっても野茂という若い野球人を認め、更に応援することも忘れていない。野球と人間を愛する著者は本書の題にしても長嶋監督という多分に人間的な魅力を持つ人物に対して敢えて苦言を呈することで本心は日本のプロ野球が人間の心に感動を与えることを願って止まないという熱気が伝わってくる。本書を読んでいると野球は技術だけではなく、人間対人間の熱きドラマであると痛感する。それは氏が最後の方に取り上げている野球人ではないが「江夏の21球」を著した今は亡きジャーナリストの山際淳司にしても同じ気持ちだったのだと思う。江夏氏の野球に対する必死の姿勢は最後に述べられているこの言葉に集約されている「くたばれ!ジャイアンツ」「がんばれ!タイガース」
大前研一/青春出版社/239ページ/1997/97.6.26
大前氏はこの本の中で現代日本に横たわる問題を8つの大きな章に分けて、問題提起-解説-解決策という流れで読み説いている。その8つを列記すると1.「茶番劇」に蠢く次の図式(利権をめぐる密約)2.保険、金融その巧妙なる「すりかえ」を見破る(破綻の正体)3.まだまだある損失補填「先送り」の醜態図(しわ寄せの構造)4.「日本株式会社」の裏の力関係(国と企業の共謀)5.「幸福な社会」に隠された悪魔の制度(「福祉」の次なる食いもの)6.日本の景気は「まやかし」から滅びる(「見えない税金」の手口)7.3年後、5年後の経済を揺るがす国際的「カラクリ」を明かす8.人災の”日本大不況”からの脱出という日本の深刻な問題の数々である。それを国際的な目を持つ大前氏らしく国際事情なども鑑みた上で様々な頭にくる事例を挙げて懇切丁寧にしかも的確に解説している。ただ、通常の氏の著書と違うのは文章の書き方がかなり怒気を帯びたもので語尾がいつもに比べて少しぞんざいという印象である。それは別に悪いという意味ではなく、それほど日本の現状に憤りを感じて、とにかく書かずにはいられないという風に私は採った。私自身もものすごい怒りを感じているし、本書も氏の怒りと共に一気に読んでしまった。これらの問題は無関心ではいられないし、そんな問題意識では日本はもう良い国には成り得ないだろう。本書を含めて大前氏の著書は読むだけではなく、それぞれを現実の問題として一人一人が解決策を模索して、その解決策を明日からでも実行して頂きたい。疑心暗鬼に成りすぎるのも問題だが「もう騙されないぞ!」という気概はいつも持っていたい。
福田和也/角川春樹事務所/173ページ/1997/97.7.4
私は前著で福田氏の表現を稚拙で下品であると扱き下ろした。しかし、本書では大幅に改善され、表現が丁寧になったのとは反比例して、前著より以上の氏の母国に対する耐え難い怒りを感じた。特に帯にある言葉「醜い日本人に生きる価値はあるのか」という表現に関しては私自身も「現状の日本人と思しき人間共には生きる価値がない」と断言したい。福田氏はペルーのリマで起きた人質事件の対処の仕方をペルーのフジモリ大統領と日本の橋本首相を比較して、前者を「テロという暴力に屈せず、正義を貫いたサムライ」と評価し、後者を「何もせずに安全地帯にいて不埒な発言をした卑怯者」であると酷評している。その後は愛国者であると自称する著者が現代の日本人を近代に生きたサムライと比較することにより現代人は「名誉」というものに対しての極端な感覚欠如、そして暴力に抵抗する「気概」「勇気」の著しい欠落が見られると述べている。この体質が厚生省.岡光某の不祥事や女子高生売春、野村や第一勧銀の総会屋問題などを起こした原因になっていると力説している。この後に帯にある象徴的な言葉が出てくるのである。私も福田氏の熱情的な分析や力説されている日本人の堕落に関して一切反論するべき事はない。ただ、後半の教育の部分で現在の個性を重視する教育には決定的に人間観が欠けていて、「よき日本人」を育成するという視点がないという意見はその通りだと思うのだがだから人間が出来ること、選べることは限られているという教育をしなければならないという主張には些かの異論がある。それは確かに現在の人間の尊厳を忘れ去ってしまった日本人には必要かもしれないが長期的に見ると武士の志や夢をも否定してしまう事になりはしないか。福田氏の言わんとするところは自分の身分と能力を弁えた上での尊厳のある人間としての生き方であると思う。だが、余りに早期から自己認識を強制させることはその後の人生に於いて非常に大きすぎる足枷である。氏は大学の授業でも学生に実際にそう話していると著述しているが早計にそういう事は判断するべきではない。世論に阿らない福田氏が一方的に走るのではなく、この項目以外の考え方を理解出来る人間を一人でも増やすことの方が肝要だと思う。それは時間のかかる作業かもしれないがここまで堕落してしまった人間達を尊厳のある日本人に戻すには一朝一夕では行かない。我々もお互いに独自の考えで「焦らずしかも早急に」よき日本人を形成して行きましょうよ。私は決して日本人にそして母国にも絶望してはいない。
大月隆寛/洋泉社/393ページ/1997/97.7.6
大月氏が1989年から94年まで遊撃型言論雑誌「別冊宝島」に書き下ろしていたものを編集した本。氏自身が「若気の至り」と表題している通り、思想の中に30歳から35歳までの今よりは一寸若い大月氏の拘りが其処ここに見受けられる。私がその印象を一番感じたのは300ページから始まる「大宅文庫のフリーライター」と題された章である。この中で著者が大宅文庫の資料の分類やカードの整理など裏方役である中澤氏にインタビューする場面がある。中澤氏は多数利用しているいわゆるギョーカイの現在の若いライター達の印象を語り、その上で苦言を呈している。氏によると彼らの印象は「調べる目標がはっきりせず、調べることに対して淡泊であり、物事のツッコミが昔の人々より足りない」と述べ、苦言として「書いたことに責任を持って欲しい」と熱望している。大月氏もこの章を振り返る文章で述べられているが大宅文庫で得たネタを使い回しで雑誌などに掲載しているライター達にはジャーナリストとしての正義だとか名誉だとかは存在しないのだろうか。彼らにとってギョーカイにいるということは只、女にもてたいとか、かっこいいなどの理由しかないのだろうか。こんな使い廻された雑誌などの情報で一喜一憂する我々一般人は大宅氏の言葉ではないが「一億総痴呆症」という相当な重病に罹っているのである。大月氏の言葉を借りれば「言葉によって支えられる信頼感が存在しなくなった」のだ。無責任な体質は官僚や会社だけではなく、正義と名誉に支えられた情報提供をしなければならないジャーナリズムやライターの世界にも深く進攻している。これも氏のように若気の至りとは言いながらでも不器用に生きようとする人間が減ってしまったことに起因しているのである。そこに情報があっても自分の頭で考えることを放棄してはいけない。
日本経済新聞社(編)/日本経済新聞社/250ページ/1997/97.7.8
日本経済新聞紙上に連載中「2020年からの警鐘」シリーズを再編集したもの。一つ一つの項目はなるほどと思わせる部分の章が多かった。だが最後のページに掲載されていたその警鐘をならすべく集められた「日経2020年委員会」のメンバーを見ると愕然とした。殆どが大学教授で占められているのである。これは私の独断と偏見だが日本の大学教授とマスコミに頻繁に露出する知識人と呼ばれている人種ほど現在の政治家以上に無責任でいつまでも結論の出ない不毛な論議を続けている輩はいないと思っている。本書の中にも述べられていたが日本でこの様な委員会成るものを作るとどうしても一般市民を中心としたものではなく、こういう名のあるメンバーで編成されてしまう。もし借りに会社で下の者が一般人を選んだとしても「日経」などという大看板を背負っていると上の者が有名人を使うことを指示するであろう。それが下らない面子なのである。内容がどうこう言うより日本ではそつのないことが重要視される。(それは株主総会で証明済み)本書の内容は全体的には余り危機感の感じていない日本人に警鐘を鳴らすという事で実に様々な事象がうまくまとめられているのだがどうしても大学教授、知識人や一流会社の経営者など上から物申している感は否めない。一般人のコメントも載っているのだが日経の主張に合わせるよう取って付けたような談話が多い。だから結果的にこの本の題名ほど切実な印象は受けない。同じ2020年からの警鐘という本であれば、ピーター.タスカ著「不機嫌な時代-JAPAN
2020」の方が良い意味でも悪い意味でもひしひしとこのままでは日本の沈没して行く姿が実感出来るという点で数段上である。本書は現実に起きていることを認識するために只単に資料として読むのならいいが本当に日本を良い方向へ導くための実行書として読むには非常に客観的過ぎると思う。読後感は世界中で日本の窮地を一番旨く表現出来ないのが我々日本人に他ならないということである。
タイム.ライフ(編)、北代晋一(訳)/同朋舎出版/294ページ/1995/97.7.27
本書は「神戸小学生殺害事件」の容疑者が参考にしていた又、読んでいたということから一躍有名になった。特に一番最初に出てくる「ゾディアック事件」を真似て、容疑者が犯行に及んだのではとの憶測もされている。具体的な犯行の経緯は皆様の方がご存じだと思うので除くとして、まず両事件を比較すると特に類似しているのは「犯行声明文の書き方」「犯行声明文の出し方」「犯行声明文の構成」の3つの点だと思う。細部では異なっている部分も見受けられるが全体の姿は驚くほど似ている。その部分については例え興味本位でもいいから本書を購入して是非一読していただきたい。その他にも3つの非常に興味深い未解決殺人事件が掲載されている。「評決」「映画監督の死」「消えたホッファ」-これらの事件は調べたわけでないから正確なことは言えないが華々しくマスコミを飾った事件だからおそらく映画化されているであろう。だが、その映像より文章の方がひしひしと迫り来る恐怖感や背筋を伝わる人間の冷酷さをより一層感じることが出来るであろう。又、最後まで本書を読んでふと考えたことだがこれらを未解決にした最大の原因はそれを取り巻く人間だということである。それはモンテスキューが「法の精神」で説いた三権分立が米国と雖も完全に機能していないことを証明している。それぞれに関わっているのが人間である以上、彼らの行動様式は法にだけ縛られてはいない。それらを決定するものは感情、金、権力、女、組織、マスコミなどに纏わることが多い。これらを排除すれば犯罪の解決率を限りなく100%に近づけることが可能なのだろうが現実の社会に生きている限りそれは不可能であろう。私としては米国、日本を問わずに世界中に正しい良心の下で行動出来る人間が増えることを祈るだけである。私も自己の良心に呵責を起こさせる行動だけは慎んで行きたい。
野尻義明/主婦の友出版/311ページ/1997/97.8.12
なんでだまされるの?「でも、だまされちゃったんだなあ」というのが私の正直な感想である。恥を晒すようだが私もだまされ未遂が一件、今考えるとだまされたのが一件、自分から突っ込んだ確信犯が一件の計三件は確実に悪徳業者及びサラ金のお世話になっている。現在もカードキャッシングのお世話になることは度々あるがなんとか支払いが給料の範囲内で済んでいる。まず、最初のだまされ未遂は私が神奈川県の大学に通っていた時に下宿に掛かってきた「貴方は選ばれた人です」という本書にも登場する典型的な悪徳業者の手法の餌食になったのである。内容の詳細は忘れてしまったが35万する英会話の教材を買えば、旅行やスイミングクラブの優待会員としての特典が付き、更に契約する海外の施設なども格安で利用出来るというものだったと思う。そして、その会社の所在地が新宿西口の高層ビル街にあり、そこに来て欲しいという。札幌から出て来て、そういう場所への憧れもあり、私はその男の言葉を信じ、そこのとある高層ビルに向かった。そして結果的には彼の巧みなセールストークに負けて、契約してしまう。収入もないのにである。親からの仕送りで月々の支払いは賄えるなどと親が聞いたらなんと親不孝なと思うことを平気で考えていた。だが、下宿に戻ると段々と不安になり、相手に電話を掛け、なんとか解約することが出来た。幸いに書類を後で提出するとの事だったのが救いであった。それから今考えるとだまされたと思うのが占いハウスによる500円で運命鑑定という看板に釣られたことである。確かに運命鑑定は丁寧にやってくれたのだが本当の目的は今も私の手元にある運命を開眼させるという水晶で出来た3本で約30万円の印鑑である。その時は信じていたのだが後で冷静になって考えると運命を餌にだまされたのである。最後の自分から突っ込んだ確信犯というのは26歳頃、札幌.すすき野でスナックのねえちゃんに入れ込んで週に4回は店に通うために3軒のサラ金からキャッシングを繰り返し、合計100万円近い借金を作ったことである。この解決方法はお袋の素早い機転により俺の月々の借金を肩代わりしてもらった。本当は一生彼女には頭が上がらないのだがそんなことは忘れたように今でも時々悪態をついている。本書を読んでこの様な過去の忌まわしい事が蘇ってきた。野尻氏も再三再四、述べているようにやはりだまされる本人が悪いのである。こんな私が言うのもなんだがだまされないためには本書や消費生活センターなどで常に新しい知識を吸収し、自分自身で気を付けるしかないと思う。そして、その得た知識から素早く悪徳業者を見抜く目を持ち、彼らを敢然とした態度で徹底的に排除しなければならない。それから私の如く、自分の方からわざわざ借金地獄に首を突っ込む必要はさらさらないのである。これからは自己責任の時代であるから自己を防衛していく以外、防ぐ方法はない。
高橋審也ほか/宝島社/287ページ/1997/97.8.31
この本を読み終わっても何だか釈然としない気持ちが残っている。この本の題名を北海道新聞の中に見つけた時は昨今起きている残虐な殺人事件の原因の一端は掴めるかなと思ったがそれはとんでもない間違えであった。副題にある「彼や彼女はなぜ、人を殺したのか?」という疑問は最後まで解けなかった。只、一つだけ何となく納得したのがある囚人経験者の話で殺人者には二通りいる。一つは元々異常性格を持つ者と普通の人間が止むに病まれず殺人を犯してしまう場合だ。前者の場合はもうどうしようも対処のしようがないが後者の場合は限界のある一点を超えて殺意が芽生えたのだから冷静に戻った時には真人間になっていると述べている点である。それはどうしようもない衝動の中での人間の心理の弱さを見事についている。だからこういうことを背景として、そして神戸の事件を通じて少年法のあり方だとか死刑擁護論や廃止論が盛り上がっている。しかし、筆者自身は死刑制度を肯定している。それは何故かというと元々の異常性格者を真人間にするのは不可能だからである。この人間達は性悪説でしか論じることが出来ないのである。そういう人間達にはやはり極刑を持って臨むしかない。だが、それ以外の人間達については救いの手を辛い思いを受けている被害者の遺族の同意を得て、共に考えても良いのではないか。十把一絡げに日本では論議がなされてしまうが人間を見極めることが大切だと思う。その辺りに柔軟に対応出来る法律改正が成されるべきである。少年法も少年院にいる長さや罪を重くすることばかりに比重を置くのではなく、その人間を客観的に見れる人間(教育者)を作ることが肝要である。日本の教育及び社会で根本的におかしいのは人間を見る目を養っていないということである。なんでもお金だとか地位だとかで単純に判断してしまう。人間が窮地に追いやられた時に助けることが出来るのは人を正確に見れる良心を持った人間しかいないのである。これ以上、「隣りの殺人者」を助長するのもくい止めることが出来るのも良心を持った隣人しかいないのかもしれない。
斉藤貴男/文藝春秋/391ページ/1997/97.9.14
「超能力」「永久機関」「呪術師」「オカルト」「万能EM」「船井幸雄」「ヤマギシ」「カルト」-これらは本書を形成する主要な言葉で皆さんも一度はどっかで見たり、聞いたりしたことがあると思うがこれらがまさかここまで各界(経済、政治、行政、農業、科学他など様々な分野)を浸食し、現在の資本主義に蔓延っているとは...。この閉息状況の中で本書に抜粋されている日本のシステムを語るのに特徴的な文章がある。「日本のシステムは、少数の優れた人の才能を最大限に発揮させることを可能にする制度ではなく、またそれに依存するものでもない。それは、多数の平均的な人たちに安定した環境を提供し、その職場内により多くの自由を与えることによって、仕事をより働きがいのあるものにし、そこから生まれる多数の人間の集団的活力に依存するシステムなのである。つまり、企業主義は、少数の才能ある人間が報われることは必ずしも多くはないが、多数の平均的な人間にとっては、より有利な体勢なのである」これは実に現在の日本の労働システムを的確に捉えた分析だと思う。どちらかというと資本主義というよりコルフォーズやソフォーズが存在したソ連の社会主義理念に近い。そしてこれを更に著名人が実体のないニューエイジ的カルト性(新霊性)論理を持ち出すことによりその独特な精神社会の中に個人を埋没させ、企業に滅私奉公させる日本的労働システムをもっと推進して行こうとするものである。その旗頭が多くの人々に影響力がある船井幸雄であり、稲盛和夫などである。書店に並ぶ最近のビジネス書と呼ばれているものの中に可成りの数、彼らの著書も含めて、非常に耳障りのいい言葉を弄した精神カルト的書物が幅を利かせている。しかし、一般人がここで忘れてならないのは新霊性論理を伝える彼らの本当の目的を良心に基づく自分独自の原則を確立し、きちんと見極めることである。人間以外の神などを用いて精神論を語りながらも彼らの心の奥底には個人から思考力を取り去り、企業の論理や理念を洗脳しやすくしているのである(この辺りはオウム真理教や統一教会となんら変わるところがない)。言っていることの大部分はこれから「21世紀に向けて、個人の生活をもっと快適にする」などという私達にとって好ましい事などでは決してなく、これまで以上に日本企業教の信者を増やし、彼らにとってコントロールしやすい様に環境を調えることなのである。彼らの言葉や行動をこれからも信じる人は教祖様を死ぬまで崇め奉り、現世で自由を奪われたままあの世に行く覚悟が必要だ。人間は弱いものである。だからといって自己の人生を他人に委ねては生きていく価値がない。喜怒哀楽という感情は人間にとって絶対に必要不可欠なものである。この中のどれが欠けても人間という種ではない。
マークス寿子/草思社/229ページ/1997/97.9.18
英語や日本語という言語に対する考え方や現在の日本に於ける男女の関係などこれまでもこう言っては彼女の失礼かもしれないが自分と考え方や感じ方などが似ているなと思っていた。それが本書では自分が著述しているのではないかと錯覚するほど、強く共感している内にアッと言う間に一気に読んでしまった。殆どが同意見だった上に179ページから始まる「甘えつづける日本女性」で大腸菌O-157が学校給食で集団的に発生した時、何故日本の母親たちは自分で子供達の安全を守るために弁当を作ると言わなかったのかというくだりでは思わず膝を叩いてしまった。実は私も全く同じ事を考えていたのである。これだけ給食が子供達に恐怖を与えているのに「うちの子供にはそんな危ない物を食べさせません」と毅然とした態度で拒否し、どこかで母親たちが団結したという話は聞かない。日本が安全ということに政府だけではなく、本能的に子供を身を挺しても守るべき親ですらその役目を果たしていないどころか危機意識が完全に欠落している。また、私も「THOUGHT」のページで書いたのだが一般家庭では家族サービスという名の下に「休日がイベント化」(118ページ)してしまった。それでも自分達で工夫してそのイベントを構築するのだったらまだいいのだが大抵は企業の商業主義に乗り、既にお膳立てされたイベントに親子とも共参加するだけなのである。貴重な休日を頭を使わずにベルトコンベアー上で家族団らんを演じているだけだ。そこから得るものは「行った」という事実以外ないであろう。この見せかけだけの空虚な休日を子供の頃から何回も過ごしていたら人生を楽しいものだとは感じなくてもおかしくない。これは私事だが小さい時は幸か不幸か親父が典型的な企業戦士だったので休日などは遊んで貰った記憶がない。常に休日は親に頼ることなく、自分で考えて過ごさなければならなかった。特に私は昆虫や動物が好きなこともあって近くの山、川、沼などでそれらを捕まえて遊ぶことが多かった。今、考えると幸せな少年時代だったのかもしれない。話は横にそれたがマークス寿子さんも再三述べている通り、日本はお金というモノに全ての魂を抜き取られ、倫理や道徳心をどこかに置き忘れてしまったのである。置き忘れたものならもう一度、そこに戻って拾ってくれば良いではないか。本書も含め寿子さんの著書を読んで(小生のTHOUGHTのページも偶にお願いします)もっと「日本を憂う人々」の割合が増えて欲しい。悲観することはない、未だ間に合う!!
秋川ヨシオ他/宝島社/271ページ/1997/97.10.1
116の別冊宝島333「隣の殺人者たち」に続くもので内容的には117の「カルト資本主義」と類似している。因みに表題の「トンデモさん」とは従来の科学信仰に囚われず、以下の項目のような研究を本人はいたって真面目にしている人々のことである。「波動、UFO、フリーエネルギー、未来科学、ゴースト・バスター、インチキ博士号、絶倫天文学、タキオン、全知全能研究、珍特許、地震予知、カタカムナ、高次元科学などなど」しかし、段々と読み進める内に世の中にメークミラクルを興そうと懸命にやっているこれらトンデモさん達は実は商業主義などに乗って他人を巻き込みさえしなければ愛すべき人々なのではないかと思い始めた。そして彼らは自分の好きなことで人生を楽しんでいる幸せな人達でもある。それらと比較して、本書の最後の方に書いてあったがこれらトンデモさん達よりも現実の大学や研究機関に於ける本業である自分の研究を殆どせずに名誉と金が欲しいばかりに権力闘争に明け暮れる現実科学信仰者達の方が非常に滑稽に映る。彼らはトンデモさん達を頭ごなしに批判するばかりで客観的に実験などで決着を付けようとしない。間違いをきちんとした形で証明出来ないところに現実科学信仰者達の堕落が存在する。だがそれは科学の世界だけに限らず、現代社会は平静からの「地道な努力」という謙虚な言葉を消滅させてしまった。それならば、現実逃避をして、空想の世界に埋没しようとしても無理からぬ事である。それを個人の責任に於いてやるぶんには全然構わないと思うが船井某大先生の様に世の中の大勢の人々を路頭に迷わせるような発言や行動は慎むべきである。それでは宗教や空想の世界に逃げ込まずに現実を見つめて行くにはどうしたらよいかと?それは反対の意見や自分が受け入れられない生き方をする人間達がいても感情で全てを決め付けるのではなく、人間らしい理論や良心に基づく自分で構築した原則を持って対することである。その意味で「トンデモさん」の奇特な存在は人間の生き方と世の中の方向を考えるのに役立つと思う。
堺屋太一/講談社/326ページ/1997/97.10.9
私は常々右肩上がりでお金だけを中心にやってきた日本国と日本企業は軌道修正の時期に来ていると言ってきた。それが本書で堺屋氏によって明確に指摘されている。一寸何年前に出した著書の予想がピッタリ当たったなどという表現がしばしば引用され、押し付けがましい点もあるが。それにしても第八章の「新・人材革命」が母国の将来を考える上で肝要だと思われる。バブル以降の「俯き加減の時代」に於いてはこれまで日本を牛耳ってきたような官僚に特に多い「試験人材」などでは乗り切れないということだ。試験人材は答えの決まっていないものに答えを出すのが一番苦手な人材なのだ。この先行き不透明な世の中でそういう人間達に日本丸の舵取りの出来る道理は全くない。堺屋氏はこれからを支えて行く人材として「能力が高くて意欲のない人間」を挙げている。これを読んでいる大いに意欲のある人間は「どういうことだそれは」と憤るかもしれない。詳細はここに書けないので本書を是非読んで欲しい。ただ言葉を少し補足すると「俯き加減の時代」では何もかも前向きではなく、やることと止めること、拡げることと縮めることを正確に区別できる人間が優れた人材であると堺屋氏は説いている。これとは全く正反対の人材が昨今の証券業界スキャンダルで登場する人物達である。彼らは他人に比べて意欲だけが異常に高く、会社のために...と法律に触れることを進んでやってしまった。結果としてはやることと止めることの区別がつかず、会社に多大な損害を与えてしまった。これらの事件ではこういう人材を積極的に会社の推進役に任命してきた企業自身にも大きな問題がある。しかし、現在の日本では民間や官庁なども含めてこの様なやる気のある人間を評価する企業が殆どなのである。この問題は決して対岸の火事ではない。何時、自分の所に飛び火してくるか分からない。これからは選ぶ側もこういう人材を勇気を持って、要職につけないような心構えでいて欲しい。また、個人としては氏が最後に述べているように「集団への関心を失わない個の確立」が必要でそれは自己で確立した原則を基に家族に対しての思いやりなど自然な人間性を忘れないということで生きたい。だから本書の題は「次」はこうなるという客観的なことではなくて、「次」はこうする!!と積極的に言い切る。
日本経済新聞社(編)/日本経済新聞社/275ページ/1997/97.10.15
112.2020年からの警鐘-日本が消える-の続編。前著もそうだが現代日本の様々な問題点を非常にうまくまとめているという感じがする。そしてうまくまとめていることは認めるのだが低迷を続ける日本サッカーと同様で何か綺麗すぎるのである。本当に泥臭い心からの雄叫びでなく、警鐘でもない印象は拭えない。それは前著でも指摘したこのプロジェクトに参加している人物達に起因しているのではないか。「日経2020年委員会」全19名のメンバーの内訳は15名が大学教授、3名がシンクタンク関連、1名が経済評論家である。それぞれが各業界に於いて権威のある人々である。だが、当然の如く権威があるという事はかなりの実績を過去に積んできているということで当然年齢もそれなりの年である。失礼だがもしかすると2020年には亡くなっている方もあるのではないか。だから私はそんな人々に2020年を語らせても本当に責任を持った未来像を描けるのだろうかという疑問を抱く。本書は日経新聞を良く読み、年をとってからはからっきし権威に弱い団塊世代の人気は集めるであろう。けれど、若年層にとってはおやじのぼやきにしか聞こえないかもしれない。若い人々に必要なことは本書を読んで「おやじ達、何言っているんだ」という批判精神から自分達の頭で日本を再構築し、行動につなげていくことだろう。そのための反面教師としてはいい教材かもしれない。そういう意味からも中に書いてある事柄に関しては非常に納得出来る部分も多いのである。これからは日経さんに頼みたいのだが「日経2020年委員会・若年の部」を結成してもらえないだろうか。中心は20代のベンチャービジネスの旗頭達である。2020年にはこれらの人々が社会の中心として活躍しているのは間違いない。もしかすると「怠慢な日本人」というのはこれら社会の中心になるだろう日本の若年層の力を素直に認めず、その上、彼らに考えさせない人々なのかもしれない。
轡田隆史/三笠書房/252ページ/1997/97.10.17
轡田隆史/三笠書房/248ページ/1997/97.10.19
小生のこのページにピッタリの題名である。本屋で偶々PART2を見つけたのでこっちから読み始めた。これも朝日新聞論説委員である轡田氏の言う「逆転の発想」で2から読んだ方がより1を読んだ時に理解が出来るのではないかと私なりに勝手に解釈した。2の方で特に印象深かったのは第4章「批判する力、批判に負けない力」で批判というのは何かをしたことに対する勲章なのだと述べている。私はインターネットのホームページを立ち上げてからもう1年半以上になる。その間には様々な激励の言葉や意見、批判を多くいただいた。その中で批判に関してはいつも猛然と反論を展開し、あまつさえ主張を理解してくれない人間は二度と自分のホームページを見てくれなくて結構などという実に独りよがりな心の狭い態度で接してきたように思う。実は批判をメールでくれるということはそれだけ自分の書いたものを真剣に読んでくれている証拠なのであると気づいた。だから激励の言葉以上に批判の声に対応しなければいけないのである。これからはもう少し大きな心を持って、自分のホームページをもっともっと充実させていきたい。また、氏は「考えるプロセス」として知ったか振りを止めることを奨励している。だから「一を聞いて十を知る」のではなくて「十を聞いて一を知る」くらいの問いかけが必要であると。その上で知識は必要であるが必ずしも考える力とこれらは比例しないことも。人がある事象に対して素直に感動し、素直に疑問を抱く態度が考える力を養うのである。知識に頼るとどうしてもこの素直な態度がなくなってしまう。高みから物事を見、聞き、感じては本当の感動を得ることは出来ない。又、1の方では第8章「書くことは考えること」で普段何気なく使用している言葉の意味を知ることが肝要であると痛感した。私自身も国語辞典や英和辞典などを手元に置き、直ぐにわからない単語があれば調べるようにしている。しかし、普段使っている言葉についてはその意味などかなり無頓着なところが多い。(これも知ったか振りの一種かもしれない)氏の著述によってこういう言葉こそ意味を知るべきであると考え直した。私はこの2冊の中で特に前述した部分が印象に残ったが人それぞれによってそれは異なると思う。そういう点でも本書を「考える力」をつけるバイブルとして是非皆さんに読んでいただきたい。現在でも本書は40万部を突破しているみたいだがさらに多くの人に目を通して実践して欲しい。
石原慎太郎/光文社/249ページ/1997/97.11.1
慎太郎氏の論調はいつも何故かすがすがしい。それは「平等」でないからだ。論じるということはどちらにもいい顔をする八方美人のようなことではいけない。その述べられたことを判断するのはあくまでも読者であり、聞いている者達なのである。本書の感想に入ると戦後50年以上も日本は不当な米国に与えられた憲法の元で男女は平等であることが義務づけられて来た。未だに仕事など社会的な面では女性に不公平な部分を強いているところは多々あるがこの変な「平等意識」が人間の性としての「男」と「女」という根幹を揺らがしたことは間違いない。それは氏も書いている通りにお互いに依存する体質の夫婦生活を営んでいる男女に顕著に見られる。夫が妻や子供に対して「父性」を発揮出来ないのである。つまり、自分の考えではなしに妻や子供の要求を殆ど無条件に受け入れることが結婚生活を持続する最大の鍵になっているのだ。例え毎日、妻や子を養うために一生懸命仕事に勤しんでいてもだ。当然こんな関係の中からは父親を尊敬するなどという心は生まれてこない。下手をすると妻と子供が徒党を組んで父親をばかにするという事もあり得るし、実際に多く存在する。子供は当然父親の影響(父性)を受けない片親(母性のみ)として育ってしまう。こうして片輪の人間が数多く製造されることになる。これに「子供の人権を認め、体罰は絶対しない」などという甘っちょろい考えの学校教育が益々拍車をかける。著者は数十年前に当時大変話題になった「スパルタ教育」という本を出した。私も小学生の時にこの本を読んだがそれでその頃の母親の体罰の意味や普段は黙っているがいざという時に手を出したり、責任を果たす父親の態度を少しは理解出来た覚えがある。先生も生徒に対する時は毅然とした態度であった。そして慎太郎氏は本書ではこの現代日本の「父性が存在しない」というゆゆしき問題に江戸時代の武士道に見習い男性が男としての責任を果たす「父性」の復活が絶対に必要だと説く。それはもちろん家庭でもそうだが学校の先生に於いても肝要なのである。私は常日頃から個人的に充実した生き方をすべきだと主張しているがいくらそうは言っても人間は家族や学校、職場などで他人との関わりを絶つことは出来ないのだから。その関わりの中で「父性」「母性」をハッキリと示していくべきであろう。この前、ある新聞のアンケートで過去を語ることや振り返ることがオヤジやオバンの一番の特徴だと掲載されていた。冗談じゃない。君らは身近な人から歴史を学ばずして、誰から歴史を学ぶというのか。それに値しない人も多いかもしれないがさりとて全く皆無でもないのだ。現在、学校の歴史教育は全然当てにならないし、君たちが改めて古典などを紐解くなど夢物語だろう。それならばそんなことで即下らない判断をしないで生きている周りの先達に素直に歴史について聞いてみる方が良い。それから最後に周りの大人達(特に男)は金をまき散らす修行中の学生に「ダメなことはハッキリダメ」と言って、我慢させることを学ばせて欲しい。それと最近マスコミに注目され、いい気になっているその辺のへなちょこ思想家は慎太郎氏を見習い、手前が論じる時には命をかけた武士のようにきっぱりと退路を断ってくれ。
野坂昭如/PHP/308ページ/1997/97.11.6
大島渚を殴った頃から単なる酔っぱらいのオヤジと思ってテレビを見ていた。だが、「オヤジ手前も考えてるじゃねぇか」と読み終わって率直に感じた。特に「自国語を身につけねば民族は滅びる」「子供に死顔を観せよう」「歴史は親が子供に伝えるべし」この3つの項目は常日頃私も思っていることなので非常に共感した。「自国語...」についてはマークス寿子さんの著書などの感想で述べているのでここでは省く。「死顔...」については私自身の経験も交えて語りたい。本書で野坂氏が最初に死顔を見たのは小学校5年生、11歳の時と書いている。実は私も死顔を初めて見たのは11歳の小学生であった。当時旭川に住んでいた母方の祖母が亡くなった時である。祖母が危篤になった時の母の姿や葬式の時の周りの様子など今でもハッキリ覚えている。白い菊に包まれた祖母の死に化粧を施した顔をまじまじと眺めた。そして、棺を閉めるために石で釘を打った。厳かな葬式が僕にとっては初めての経験だったのでどれもこれも新鮮に映った。そして数日後、自宅に帰ると何故かこの光景が頭から離れずに「死んだら自分もあんな風になるのだろうか」「死にたくないなぁ」などと思っている内に眠られなくなってしまった。こんな事が2-3日続いた。この時、幼い僕なりに「生とは?死とは?」と考えたのだと思う。僕が死の事を漸く振り切ったのは日常で仲間達と野球などをしている内に記憶が段々と薄れていった時である。しかし、この時に僕の死生観が出来たのだろう。今でも時々思い出すことがある。それとこれは余談だが葬式場のいちょう並木で銀杏を拾っていた私はその後、いちょうの菌で肌にぼつぼつが出て、酷い目にあった。話は脱線してしまったが氏の言う通りに生死を考えるという意味でも中学生以前に死顔に出会うことはその後の人生で重要なことだと思う。「死は遠ざけるものではない。生は近づけるものではない」これは勝手な憶測かもしれないが神戸の事件の少年は可愛がってくれた祖母が死んだ時に本当に自分で死顔を間近に見たのだろうか...。長寿は良いことなのかもしれないがその事が実は益々人間を死から遠ざけている。でも、ただ死ねば問題が解決するというものではない。これについては私自身ももっともっと考えて「THOUGHT」のページに改めて書きたい。「歴史...」については123の石原氏のところでも述べたが野坂氏も語るように現在の歴史教育が全く当てにならないのだから身近な人々から貪欲に歴史を学んで欲しい。又伝達する者も口コミで伝えることによって歴史を風化させずそして、その当時の人々を悪戯に誹謗中傷せず、歪曲しないで伝播してもらいたい。正しい歴史の伝承もその時代に生きる人々の未来の人々に対する義務なのである。
神山敏雄/光文社/241ページ/1997/97.11.16
「野村証券」「第一勧銀」を発端として続々と検察特捜部によって企業の悪行が暴かれつつある。数々と逮捕される事件の張本人達、自分達の責任を回避しようとする右往左往する会長や社長を頭にする役員達。事実は"ムラ社会の掟"で張本人達は無責任な役員達によってまさに「会社犯罪の生け贄」にならされたのである。神山氏の主張する会社「性悪説」というのは企業倫理など関係なく法律を犯してまでも組織として利益追求を目指すというこれらの企業が実証していることに他ならない。本書に何回も出てくるがこれら会社のためにやったことで結果的には悪行が発覚し、会社の信用を大失墜させる。それで被害をこうむるのは会社に残された多くの善良な社員達なのである。彼らは一部の人々の暴走によって行われた所業を逆風に耐えながら長い年月をかけて信用回復に努めなければならない。本音は「何でこいつら甘い汁を吸った奴等のしりぬぐいを世間の悪評を受けながら我慢してやらなければならないんだよ!冗談じゃない!!」というところだろう。だが、これらの企業に早急に倫理を確立せよというのは現実的には無理であろう。だから会社や個人に対する法律を幾ら重くしようとも利益追求を第一義に置く以上はこの手の犯罪が無くなることはない。そういう現状から本書にもある通りにやはり自分の人生は自分で守るしかない。それは国はもちろん会社も保護してくれるわけがない。自分の手に手錠をかけたくないのなら上司の命令でも法律を犯していて理不尽であると考えたなら聞く振りをして全く無視をするのが一番よい。それでもし、責められても昨今の事件を例に出して上司を逆に脅してやればよい。その結果、会社での昇進や人間関係に響くのであれば自己の人生を第一義に考え辞めるしかないであろう。現況でもし、家族のことを考えるとなどと会社に頼るような生活をしている人々は21世紀には存在していけないかもしれない。本当に家族のことを考えているのであれば法律を破り、犯罪者の可能性を秘めている会社に在籍することの方が結果的には周りの人間に酷い迷惑をかけることになる。これら会社の経営陣達のそれまで肩で風を切って世の中は自分のために回っているなどと思い上がっていた人生が老後になってから自殺したり、牢屋で犯罪者として暮らさなければならないなんてそれまでの光り輝いた太陽のような人生を考えた時には余りにも惨めなのではないか。「有終の美」という言葉もあるように人間としては最後に生きていて本当に良かったという末期を迎えたい。
廣瀬嘉嗣他/日本テレビ/128ページ/1994/97.11.18
実は「思想」のページに「松田優作」のページとは別に自分なりの"優作論"を展開しようと思ったが丁度良い機会なので本書の読後感を通じてここに記したい。本題にあるように優作がハードボイルド・ユーモアの探偵"工藤俊作"に扮したTV「探偵物語」を現存する出演者達や当時のスタッフによって紙上で甦らせている。出演者やスタッフの優作に対する言葉も大層心に沁みたがそれ以上に原作者の小鷹信光氏の優作がドラマの中で使用したあの有名なセリフ「日本にハードボイルドの夜明けはくるのか」という文章が心に残った。その彼が法政大学の英米文学研究会の講演での現実として「ハンフリー・ボガード、優作の探偵物語」などこういう主旨からして聞き手が間違いなく知っているだろうと思う人物を若年世代の人間達は知らないことの方が多いということに愕然とする。氏はそれでも自分を慕い、ハードボイルドを卒論のテーマに選んでいるという学生に将来を託した。しかし、ハードボイルドが何たるかを分からない若者に未来を託さなければならない現状はまさにセリフの如くである。だから、その様な若年層の人々が本書を読んだからと言って「探偵物語」の本質を掴むことはきっと困難であろう。ただ、SMAP×SMAPでキムタクが真似をしていた人物と番組という実にお座なりな理解しか出来ないのが当然である。だから、是非この番組は優作出演のビデオで観賞して欲しい。そして生の優作にそして個性のあるレギュラー陣や愛すべきゲスト達に接していただきたい。この本はあくまでも優作を知る導入部である。小生も探偵物語のページなどを立ち上げ、一端に知ったか振りをしているが優作自身を知ろうとする入り口にまでも立っていないことに本書は気づかせてくれた。私も自分のホームページから優作の熱烈なファンのみんなとの数多い出会いもあったが少なくともその中で私だけは胸を張って「何十年に渡る優作のファン」でございますなどとは口が裂けても言えない。なぜなら殆ど、ファンなら所有しているはずの優作グッズなどというものも全然所有していないし、ファンならば必ず知っているという行き付けの店だとかどこそこで探偵物語の撮影が行われただとか墓はどこにあるかなどという情報についてはインターネットで知り合った仲間達のホームページを見るまでは全然興味も湧かなかったし、だからといって調べようなどという気もさらさらなかった。それでも今から17年くらい前の高校3年生の時に熱狂的な優作ファンの荒巻義隆("沈黙の艦隊"で有名な荒巻義雄の長男)という友人と国立大学共通一次試験の3日前に行った優作演じる殺人鬼・鳴海章平の遊戯シリーズ3本立て「最も危険な遊戯、処刑遊戯、殺人遊戯」には自己の人生が本当にこれでよいのか考えさせられた。(そんな考えさせるような映画ではないのだが優作のアクションが何故かその頃の身に沁みたのである)この多感な思春期に巡り会ったこれらの作品は未だに深く脳裏に焼き付いている。最近になって又見たが当時ほど感動することはなかったが既に亡くなってしまった優作が画面に登場すると凄く心が踊るのである。翻って現在は欲目ではなく、優作に匹敵するような俳優は全くいなくなってしまったが幸運にも我々は「真の役者であった松田優作の姿」をまだビデオで見ることが出来る。そして、優作を扱った本で本人を読むことも出来る。「若者よ!ハードボイルドを本当に地でいった人間の姿は現在にも残存している」のだからそこからもう忘れ去られてしまった心の襞をそして本来の人間の生き方や楽しさを学んでいただきたい。だから、私自身は「優作ファン」ではなくていつまでも「優作に人生を感化された一人の人間」としてハードボイルドな死を迎えたい。
小田晋/光文社/254ページ/1997/97.11.29
この問題については私なりに少し冷却期間を置いてから再考しようと思っていた。あの忌まわしい事件(5/27)から丁度半年経ったので本書の感想と共に述べてみたい。私は小田氏の著書を数冊読んでいるが精神医学者にあるまじき短腹なところが妙に気に入っている。そのいい意味での開き直りは144ページに現在のカウンセリングの問題点として「黙って座ればピタリと当た......らない」のが精神科診断のつねであると述べている。だから、日本では心に病むところがあってもカウンセラーより、もしかすると当たる確率が高い占い師の前に座って悩みを打ち明けることが多いのではないか。精神科医やカウンセラーに行くこと自体がこの精神の後進国ではまだ白い目で見られる風潮が残っている。それと氏も書いているがこの少年が逮捕された後、マスコミなどは一斉に責任を学校、社会や家庭に求めようとした。確かにそういう要因があることは否めないがそれはあくまでも従の部分であって、主の部分は本人の問題であり、自己責任である。だからこの少年は現行の少年法の範囲で裁けないのであれば、今後の再発防止のために一役買って貰うしかない。そのためには医療少年院できっちりとした精神分析が為されることを強く望む。それがこれまでの様な日和見主義的な分析(例えば宮崎勤)では全く役に立たない。日本に適任者がいないのであれば他の国から連れて来てでも未来に繋がる鑑定をして欲しい。また、氏が「子どもの育っていく過程」を述べた章で通常のプログラミングでは乳児期「甘やかす」幼児期「躾る」少年期「教える」思春期「考えさせる」思春期後「親離れ」となるはずが最近は積極的に社会進出するキャリアウーマンが多い日本では幼児期の躾の部分が欠落しているケースが非常に多く見受けられる。そういう関係で親が子どもの目線に立って話すということが少なくなっている。結果、こういうプログラミングで育てられた子ども達が増加すれば当然、「他人に迷惑を掛けても構わない自分さえよければいい」という援助交際等に走るコギャルの出現は当たり前のことである。確かに学校教育や社会体勢などにも様々な問題が山積しているがやはり根本の問題は人間の質である。これを現状から高めてゆくためには親と子供という基本関係をもっと真剣に考え、親は最低限、子供に基本的なプログラミングを施せるように持っていくことが肝要である。それを実行しないことには枝の部分だけをすげ替えても再び「透明な存在のボク」を生み出すことになるだろう。
フランチェスコ.アルベローニ、大久保昭男(訳)/草思社/237ページ/1997/97.11.30
訳者あとがきを読んでみると本書の原題は「オプティミズム(Optimism)」すなわち日本語にすると「楽観主義」である。「楽観主義」というと何か脳天気な感じがするが人が生きていく中でこの前向きの考え方こそが重要だと思う。又、何故訳者が日本で発行するにあたり原題を変更したかというと後述するようにこの本は「楽観主義」だけではなくて「悲観主義」も十分含まれていてそのまま原題にすると実に安直な本だと勘ぐられるかもしれないからである。それを示すように本書には62もの「何々する人」という表題があるがそれぞれが自分や周りの人々に当てはめるとなるほどと思わせられる。その最も大きな部分が日本語の表題になった「他人をほめる人、けなす人」というもので人間は自分では個人だけで生きることを願っても他人との関わりをなくしては決して生きられないという事実があるということを表している。例えば「他人を認めない人」「専制的な人」「けっしてほめない人」「他人を引きたてない」「愚かさで支配する人」など他人を蔑ろにしている人間達を会社に働いている方々ならば自分の周りに極普通に存在していることに気づくであろう。逆に139ページから始まる本当にマイペースで前向きに歩む「よりよく生きる人」に当てはまる人間の方が圧倒的に少ないだろう。著者はイタリア人だがこれは日本でもイタリアでも余り変わらないようである。又最近の倒産劇の渦中にある拓銀や山一の社員に当てはまるだろう「企業に連帯する人」「企業と一体化する人」など極めて日本人の気質を表現しているこれらの人間達は一般に仕事以外に余り価値観を見つけ出していないのが現状である。もうこれ以上、私がご託並べても本書の良さの1%も伝えられないので是非本書を1回だけでなく、繰り返し読むことをお奨めしたい。それから私は本を読まなくなったとはいっても日本人は他国から比べたらずっと本を読む国民だと思うので「本を本として読む」のではなく、「本で実行出来るところは直ぐに実行する」心づもりで日常から文章に接して欲しいと思う。(11/30現在、本書はベストセラーになっている。)
落合信彦/小学館/254ページ/1997/97.12.1
いつもの如くに落合氏の著書は一気に読んでしまう。そして、自分の人生はまだまだという緊張感と勇気を与えられる。それは氏が「自分のための自分の人生を自信を持って歩んでいる」ということである。前にも書いたがこのホームページの「THOUGHT」の項は落合氏の影響が大きい。だが、影響されているとはいっても氏の真似事をしているつもりは更々ない。俺は俺で「田畑拓也」というこの世に一人しかいない男の人生を自信を持って歩んでいる。共感する部分は多いが落合氏は落合氏だし、俺は俺である。自分なりの規範も持っているし、人間として絶対にしてはいけない最低限のモラルは充分に弁えているつもりである。それにしても数々の著書で氏が嘆いているように日本には本気で国を憂いている若者が少ないということだ。そして、迸る情熱を隠そうともせずに一生懸命に額に汗し、目がぎんぎんに輝いている若者も稀だ。このページでも何回も書いたがなにか真正面に物事を捉えることが格好悪く、斜に構えて見ることの方がかっこいいという馬鹿な風潮が蔓延っている。これはそれまでに自分の人生を真剣に考えたことがない証拠であり、常に他人を頼りにして生きてきたのであろう。その顕著な例が若者とは言えないかもしれないが倒産した後、盛んにテレビに出演する「山一の社員と家族達」である。確かに状況は最悪で同情出来る部分もあるがまず人間の最低限のモラルとして、興味本位のマスコミに自分を売り込み、それで金銭を得てはいけないということである。それは自分にとって最大の恥であり、匿名にしているとはいえ、そんな人間達を新しい会社が採用しようとは思わないだろう。自分の事にしろ、他人の事にしろ、不幸を金にしてはいけない。それと会社の責任追及は絶対にやらなければならないことだがそれ以上に大切なことは自分の足下を見つめることである。残務整理も大変だと思うが自分の人生とこの時期に真剣に向き合わないで会社の責任や悪口ばかりをしゃべっても何も前進はしないのである。「自分の出来ることは?」「自分はどうしたいのか?」「自分の目標は?」など今まで曖昧にしていたところを明確にしてから明るい気持ちで前に進むことを勧める。そのために本書は貴方の人生をもう一度真剣に考える上で一助となる。だから、私は是非、「拓銀と山一の社員の方々」に本書を熟読後、これからの「命の使い方」をじっくりと考えていただきたい。しかし、落合氏も繰り返し述べていた様に会社の人間である以上、明日は我が身ということも念頭に置き、常日頃から様々な好奇心を抱きながら自分を研鑽して生きたい。
山口猛/現代教養文庫/270ページ/1994/97.12.3
本書を読むまで山口氏はてっきり作家だと思っていた。しかし、「キネマ旬報」の取材で松田優作のインタビューを敢行した当時から現在まではフリーライターとのことである。そして彼らの出会いは吉永小百合主演「華の乱」で最悪の状態から始まった。それが優作の遺作となった「ブラック・レイン」での関わりを通して、彼らの関係も只の職業人としてだけではなく、人間としての絆が深くなっていったのである。それは色々な場面で数々登場する彼らの会話によって強く感じられる。松田優作は「太陽にほえろ!」「遊戯シリーズ」でアクションスターとして確立し、「陽炎座」「家族ゲーム」「それから」などでアクションスターとしての自分をある程度破壊し、日常を少し取り戻すことに成功する。そして、「ブラック・レイン」で日本映画の枠組みまでも破壊しようとしてそれはある程度成功したのだろう。私如きが何故"ある程度"と書いたかというと松田優作という人間は常に上昇志向で現状に甘んじなかった人間だからである。この一連の出演作の流れの中で彼の心の内の葛藤が山口のペンと優作に対する愛情を通じて、自分の心に染み込んでくるである。又、ファンにはたまらないだろう随所に散りばめられている雑誌などの"優作語録"が彼の深い人間性を如実に表している。松田美由紀、黒澤満、村川透、鈴木清順、森田芳光、深作欣二、そして、リドリー・スコットに至る人間同志の熱い出会いとお互いの深い理解...。山口氏との関係もそうだがこれら他の人物との人間模様も本書から十二分に感じとることが出来た。これは優作の本というだけではなく、熱き人間達の出会いの書でもある。そこの携帯電話を持って話している若い人や援助交際に走るオヤジ共には是非とも読んでもらって自分の薄っぺらさを痛感して下さい。けれど外見とは違い、こんな人間くさい俳優もついこないだまで日本に存在していたのである...。-松田優作 炎 静かに 合掌-
1← |
| →3
→3

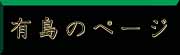 yusaku@unlimit517.co.jp
yusaku@unlimit517.co.jp